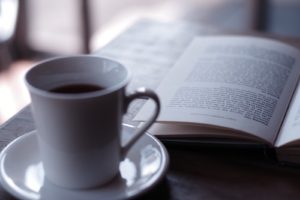「真面目」は長所か?真面目すぎて生きづらいあなたへ
真面目という性格について考える
Index
1.「真面目」は社会を支える立派な長所
2.「真面目すぎる」ことで生じる問題と、その葛藤
3.「真面目だけが取り柄」と言われた私の経験

1.「真面目」は社会を支える立派な長所
「真面目」という性格は、本当に長所なのでしょうか?
私は、紛れもなく長所だと考えています。
なぜなら、多くの真面目な人々がいるからこそ、私たちの社会は健全に機能しているからです。
特に日本は、時間管理に厳しい国です。
遅刻や遅延は「異常事態」と見なされる傾向が強く、この国の制度が滞りなく動いているのは、多くの真面目な人々が日々の職務を全うしているからに他なりません。
そう考えると、「真面目」という特性は、社会の基盤を支える、非常に立派な性格の長所であると言えるでしょう。
真面目な人の性格や行動の特徴を考えてみましょう。

真面目な人は、一つの目標に向かって結果が出るまで諦めずに努力を続けます。
規律や規範、約束事をきちんと守り、周囲の手本となるような振る舞いをします。
また、無駄遣いを控え、貯蓄に励むため、経済的に破綻することは稀です。
これらの特徴から見ても、他者に迷惑をかけることなく、規範を重んじる真面目な性格は、やはり優れた長所だと言えるでしょう。

2.「真面目すぎる」ことで生じる問題と、その葛藤
しかし、真面目な性格が問題となるのは、それが「真面目すぎる」場合に起こります。
真面目さは、一つの行動パターンを繰り返し、日々同じルーティンを淡々とこなせるという特徴を持ちます。
これは一見すると素晴らしいことですが、裏を返せば、以下のような側面として現れることがあります。
- 面白みに欠ける
- ユーモアがない
- 付き合いが悪い
- 自分のルールを頑なに守る
- 融通が利かない
- 物事を悲観的に考える傾向がある
真面目すぎる性格は、人間関係において「少し付き合いにくい人」という印象を与えてしまうことがあります。
本来は長所であるはずの真面目さが、自分をうまく表現できなかったり、遊び心が感じられなかったり、日々の繰り返しに終始したりすることで、他者からは「面白みのない人」と映ってしまうかもしれません。

真面目すぎること、あるいは真面目でありすぎることは、社会生活や社会的な評価において、あまり良い影響を与えない場合もあります。
指示されたことは確実にこなすものの、自発的な動きが少なく、主体性や積極性に欠けるというイメージを持たれることもあります。
例えるなら、「守りには強いが、攻めには弱い」といったところでしょうか。
そのため、会社組織などにおいても、現場で組織を支える側としては非常に頼りになりますが、上の立場に立つと、真面目すぎる性格ゆえに臨機応応な対応が難しくなることもあります。
また、真面目すぎる問題は、自己抑圧とも深く関係しています。
自分を過度に抑えつけて生きると、人生の楽しみや喜びを十分に体験することができません。
もしあなたが「真面目すぎるな」と感じる部分があるのであれば、少し「過ぎる」部分を緩め、もっと気楽に人生を楽しむことに意識を向けても良いのではないでしょうか。
心理カウンセリングでは、真面目すぎることによる問題、特に自己抑圧の解決に向けて、あなたの力になることができます。

3.「真面目だけが取り柄」と言われた私の経験
今から35年以上前のことです。
私の父が親戚に対し、私のことを「こいつは、真面目だけが取り柄でな」と紹介しました。
私はこの言葉に、深い疑問と、ある種のショックを感じました。
「真面目だけが取り柄」とは、いったいどういう意味なのだろう?
私にとってその言葉は、「面白みがない」、「楽しみを知らない傾向が強い」といった印象を与えました。
これは、私の生育歴において、親からの「禁止」や「強制」が強く、自分を自由に表現することを禁じられていたことに起因すると感じています。
そのため、与えられた枠の中で行動することを好み、新しいことへの挑戦や冒険をあまりしてこなかったのです。
言い換えれば、チャレンジ経験が少なく、成功体験も少なかった。

私は幼児期から親からの過干渉と、成功体験の少なさから、強い不安感を抱く青年になりました。
ゆえに、非常に慎重で、自己抑圧的、そして自己防衛心が強い性格になったのだと思います。
自己防衛感が強いと、不安よりも安全を求める傾向が高まり、他者からの批判や攻撃に敏感になりすぎたり、何事も自分に関係づけて「自分が悪く言われているのでは?」と過剰に心配してしまったりします。また、慣れた手順や失敗しない方法にこだわり、「こうあるべき」という考え方が強くなり、新しいことを試すことに抵抗を感じるようになりました。
父に「真面目だけが取り柄」と言われたのは、私が15歳前後の頃でした。 そ
れは、まさに「面白みのない青年」の姿だったのかもしれません。