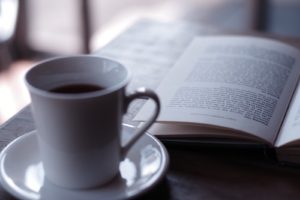「自分に興味がない」となぜ、人(他者)に対しても興味がないのか
今回の記事では、「自分」と「他者」という二つの存在を明確に分け、自分を主体とした他者との関係性について、心理的な側面から深く掘り下げていきたいと思います。
「自分に興味がない」とはどういう状態か?
「自分に興味がない」とは、具体的にどのような心の状態を指すのでしょうか?
この現象が他者との関係性にどう影響するのかを交えながら、詳しく解説していきます。
Index
1.心理的セルフネグレクト:自分を放置する心の状態
2.自己肯定感の低さと「同調性」がもたらす無関心

1.心理的セルフネグレクト:自分を放置する心の状態
「自分が自分に興味がない」という現象は、あたかも自分が自分を放棄し、心の中で「セルフネグレクト(自己放任)」の状態に陥っていると考えることができます。
実は、私自身も20代半ば頃まで、自分に全く興味がない人間でした。
当時の具体的な行動としては、鏡で自分の容姿を確認しない、他人が自分のことをどう思っているかなど、どうでもいいと思っていた、といったことが挙げられます。
ある意味、不健全な「自分は自分、人は人」という強い意識を持っていたのです。
自分の容姿を鏡で確認しないというのは、他者が自分をどう判断するかを気にしない、ということを意味します。
自分は自分、人は人、という考え方であれば、当然そうなるでしょう。

その結果、当時の私は、髪はくちゃくちゃ、大学には高校時代のよれたカッターシャツで登校するなど、ある意味個性的ではありましたが、多くの人を不快にさせてしまうような見た目をしていたと思います。しかし、当時の私には、自分の容姿が他人を不快にするといった発想も認識も全くありませんでした。
そう、「自分が他者から見られている」という感覚そのものが欠如していたのです。

a) 自分の容姿を鏡で確認しないことの意味
私たちは通常、外出する前に鏡で自分の容姿を確認し、その場にふさわしい身だしなみで外に出ます。
この「鏡で自分の容姿を確認する」という行為は、実は、他者から見られる自分を意識し、他者に不快感を与えないために行う、社会性に基づいた行動です。
しかし、自分に興味がなく、心理的なセルフネグレクト状態にあった当時の私にとっては、人に対する興味も薄く、他者の視線や「どう思われようがどうでもいい」という感覚でした。
まるで世捨て人のような格好で、大学に通ったり、外出をしていたのです。

b)なぜ「心理的セルフネグレクト」に陥ったのか
では、なぜ私は、自分に興味がない、セルフネグレクトの状態になってしまったのでしょうか?
ここには、親からの養育の問題が大きく関わってきます。
私の場合、親の養育のあり方によって、幼少期から自分を抑圧し続けた経験があります。
この自己抑圧は、結果として自分の殻に閉じこもり、社会生活を送ることへと繋がりました。
自分の殻に閉じこもるということは、他者の視線や「自分が他者にどう思われているか」といった発想が希薄になり、ただ自分だけの世界で生きている状態です。
しかし、この自己抑圧に基づく「自分の世界」に生きることは、自分を積極的に外に打ち出す機会を失わせます。
たとえ打ち出そうとしても、社会性の欠如から人に受け入れられにくく、結果的に「自分を外に打ち出す」こと自体を諦めてしまうことになります。
このようにして、自分自身に興味がなくなり、自分が自分を見捨ててしまう形になってしまったのです。

c)「自分に興味がないと人に興味がない」心理の中核
なぜ、自分に興味がないと、人に興味が持てなくなるのでしょうか?
それは、自分を外に打ち出す経験がなく社会性が育まれていないことに加え、心理的には自分の殻に閉じこもる「心理的ひきこもり」の状態にあるためです。
このような状態では、他者の視線や思いに興味が向きません。
いや、興味がないというよりも、自分が自分を「どうでもいい」と思っている以上、他人や社会のことなど、眼中になかったのです。
つまり、「自分に興味がない」ということは、自己放棄の状態であり、自分自身を放棄して心理的に引きこもっている者からすれば、他人や社会にも関心が向かない、ということになります。

さて、ここまでは私の実体験を通して、「自分に興味がないと人に興味がない」ことについてお話ししてきました。
実は、「自分に興味がないと、人に興味を持てなくなる」もう一つの心理的な理由が存在します。
それは、自己肯定感の低さと「同調性」に基づくものです。
2.自己肯定感の低さと「同調性」がもたらす無関心
よく「日本の若者は自己肯定感が低い」と言われます。
その理由を正確に把握することは難しいですが、自己肯定感が低いということは、ある意味で自分を外に打ち出すことができず、自分自身を評価できない、つまり自己否定の側面が強い状態にあると言えるでしょう。
自己否定の側面が強いと、自分自身に興味を持つような心理的な余裕は生まれにくいものです。
さらに、自己評価が低いと、他者からの評価を過剰に意識するようになります。
他者の期待する枠組みから外れないように、そのことばかりに焦点を合わせる。
ここに「同調性」の問題が生じます。

結果として、自己肯定感の低い人は、自分自身に興味を持つよりも、他者からの評価や、自分を良く見せるための「印象操作」に力を注ぐようになります。
そのため、自分自身には興味を持つ余裕がなくなってしまうのです。
加えて、このタイプの人は、他者からの評価を過剰に意識はするものの、それはあくまで「評価を得る」ことに重きを置いているだけであり、他者そのものや、人の心情、他者を理解することへの興味は薄いという結果をもたらします。
それゆえ、自己肯定感が低く、同調性に基づいた行動をとるタイプの人は、「自分に対する関心が低く、自分に興味がなく、結果として他者にも興味がない」という状態に至ってしまうのです。