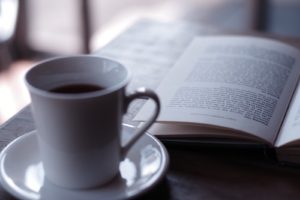子どもが苦手・嫌いと感じる人の心理と感覚:多様な心の背景
「子ども」と一言で言っても、その年齢は多岐にわたります。
この記事では、主に幼児(幼稚園児)から小学生までを「子ども」と定義し、彼らに対して「苦手」「嫌い」と感じる方の心の背景について、私自身の考察を交えながら深掘りしてみたいと思います。
個人的な要因を3つ、そして社会的な要因を1つ挙げて解説します。
子どもが苦手・嫌いと感じる、様々な心の事情
Index
1.「自己抑圧」がもたらす反発:解放された子どもと抑制された大人
2.「社会的規範」の重視:秩序を重んじるがゆえの葛藤
3.「音」への感覚過敏:静寂を求める心理
4.「地域と子育て」:希薄な交流がもたらす感覚の強化
5.子どもとの関わりがもたらす可能性

1.「自己抑圧」がもたらす反発:解放された子どもと抑制された大人
子どもたちは、周囲の環境に適応しながら、徐々に自己を制御することを学んでいきます。
しかし、成長の途上にある彼らは、感情や生命エネルギーを全身で表現し、はしゃぎ回るのが自然な姿です。
一方で、子どもに苦手意識を持つ方の中には、ご自身が幼少期に親子関係など何らかの理由で、強い自己抑圧を強いられてきた経験をお持ちの方が少なくありません。
その抑圧感は大人になっても続き、自身の感情やエネルギーの発散を抑制・閉鎖している状態にあることがあります。

このように、感情やエネルギーを全開にする子どもと、それらを強く抑圧している大人は、まさに正反対の存在と言えます。この相反する関係性では、互いに良好な関係を築くことは難しいでしょう。
子どもが苦手、嫌いと感じる方は、実際に子どもと関わる機会や経験が少ないことも多く、子どもとの接し方を学ぶ機会に恵まれていない場合もあります。
また、人は自分が自分に禁じていることを他者がしているのを見ると、不快感を抱きやすいものです。
ご自身が感情の解放を禁じられてきた方にとって、たとえ相手が子どもであっても、感情を爆発させる姿は「理解不能な存在」として映ることがあるのです。

2.「社会的規範」の重視:秩序を重んじるがゆえの葛藤
社会的な規範や秩序、ルールを強く遵守することを第一と考える方にとって、子どもたちは時に「厄介な存在」と感じられるかもしれません。
なぜなら、子どもにはそれぞれの発達段階があり、幼児や小学生に大人が求めるような社会規範やルールを完璧に理解し、遵守することを求めるのは難しい側面があるからです(もちろん、子どもも成長とともに学んでいきますが)。
また、社会の秩序や規範を重んじる方は、自己のテリトリーを守り、堅実で柔軟な対応が苦手な傾向があるかもしれません。
そして、感情よりも論理を優先する思考優位型のタイプであることも少なくありません。
しかし、子どもたちは大人の予想をはるかに超えるような、突飛な行動を取ることがあります。
(これは、子どもの冒険心や発想力を育む上で非常に重要なことです)。

堅実な大人から見れば、それは「ルール違反」と解釈され、子どもに対して威嚇したり、怒りを示したりすることもあるでしょう。
子どもの話には突拍子もないことが多く、論理を重んじる方にとっては「何を話しているのか意味不明」と感じられ、子どもがまるで「理解不能なエイリアン」のように映るかもしれません。
こうした傾向を持つ方の中には、ご自身が子どもの頃に厳しすぎる親に育てられ、その厳しさが身につき、それが高い社会性(社会における振る舞いにおける「べき論」)へと結びついているケースも考えられます。

3.「音」への感覚過敏:静寂を求める心理
子どもは元気いっぱいに大声を出したり、騒いだりして遊ぶものです。
しかし、この「大声」が癇に障ると感じる方もいらっしゃるでしょう。
例えば、家でゆっくり過ごしたいのに、外で子どもたちが大声で騒いでいる。
思わず「うるさい!」と怒鳴ってしまう方もいるかもしれません。
これは非常に難しい問題です。
なぜなら、人は静かに暮らす権利があり、大声で騒ぐことはマナー違反と判断することも可能だからです。しかし、相手は幼い子どもであり、元気に遊んでいるのは仕方ない、という側面もあります。
この問題がさらに深刻化するのは、うるさいと感じた対象に対して、人はより注意を集中してしまうという人間の特性です。

そのため、子どもが静かにヒソヒソ話して道を歩いているだけでも、子どもに対して「うるさい」という反感を持つ方は、無意識に注意が集中(過敏)になり、やはり「うるさい」、「苦手」、「嫌い」という気持ちになってしまうことがあります。
私自身も聴覚過敏の傾向があり、大きな音が苦手なため、この問題に対して「子どもに寛容になりましょう」と安易に言える立場ではありません。
そのため、根本的な解決策をすぐに見出すことは難しいと感じています。

4.「地域と子育て」:希薄な交流がもたらす感覚の強化
これまで、子どもが苦手・嫌いと感じる方の個人的な心理状態について書いてきましたが、こうした個人的な感情に対して「子どもを好きになりましょう。彼らは将来の日本を背負う立場にあるのです」といった説明は、「嫌いなものは嫌い」、「生理的に受けつけない」といった反発心を強めるだけでしょう。
しかし、一つ言えることがあります。それは、昔と比べて、「地域全体で子どもを見守り、育てる」という文化や概念が、今の日本には希薄になっているのではないかという点です。
保育園や幼稚園の数が足りない、という問題があります。
作ればいいじゃないか、という意見もありますが、「うちの近くには作らないでほしい」という声が上がることも少なくありません。

私自身、マンション暮らしで、隣にどんな人が住んでいるか知りませんし、正直なところ興味もありません。
ただ、自分の静かな生活を守りたいだけだと感じています。面倒なことには関わり合いたくない、という感覚です。
これは私の個人的な例ですが、日本全体で個人主義化が進み、多くの人が地域や近所との関わりが希薄になっているのではないでしょうか。
これが解決すべき問題なのか否か、と問われると何とも言えませんが、子どもと接する機会が少ないため、子どもと仲良くする機会もなく、地域住民の交流の希薄性が「子どもはうるさい。静かにしろ」という発想や感覚を強化している可能性も否定できません。

5.子どもとの関わりがもたらす可能性
自分を抑圧する傾向のある方、社会性が高く規範や秩序、ルールを重んじすぎる方も、もし子どもと触れ合う機会があれば、子どもに対する理解が深まり、感覚的に抱いていた子どもへの嫌悪感が薄れ、「子どもとは案外いいものだ」と思えるようになるかもしれません。
そして、ご自身が幼少期に親の厳しさから心を抑圧してきた方にとっては、子どもと接することが自身の心の解放につながる可能性もあります。
また、子どもたちにとっても、近所のおじさんやおばさんと接することで、模範的な社会性が身についたり、社会の断片を知るきっかけになったり、昔の日本のあり方を学ぶ機会にもなるかもしれません。
正直に申し上げると、私自身も子どもが苦手・嫌いだと感じる時があります。

子ども時代を「子どもらしく」過ごせなかった私としては、心理的に当然の感覚だと認識しています。
しかし、本当は子どもを通して大人も学ぶことは多々あるのでしょうし、子どもも大人を通して学ぶことは多々あるはずです。
少子化現象と、地域の人々との交流の希薄さ。
この二つが相まって、子どもと大人が自然に触れ合う機会が減っている現状は、地域における子どもと大人の関係性の分断に繋がっているように感じています。