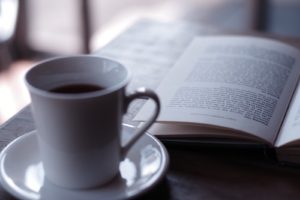困っている人を「放っておけない」:燃え尽き症候群にならないために
整体師として働く利佳子さん(仮名)は、日々お客様の身体と向き合う中で、ある悩みを抱えていました。
お客様のネガティブな話を深く聞きすぎてしまい、それを自宅にまで持ち帰って気分が落ち込んでしまうというのです。
困っている人を助けたい心理と問題
Index
1.困っている人を助けたい気持ちがもたらす問題
2.恋愛における「尽くしすぎ」の傾向
3.自己価値の確認としての「尽くす」行為
4.「尽くしすぎ」がもたらす危険性

1.困っている人を助けたい気持ちがもたらす問題
なぜ利佳子さんはそこまでお客様の話に深く入り込んでしまうのでしょうか?
尋ねてみると、「困っている人は放っておけないんです。
自分にできることは何かしてあげたい。
施術中は話を聞くことしかできないから、一生懸命聞きすぎてしまうんです」と話してくれました。
利佳子さんが整体師の仕事を選んだのも、「人の役に立ちたい」という強い思いがあったからです。
しかし、彼女の仕事はあくまで整体であり、心理カウンセリングではありません。

お客様の身体を気遣いながら施術を行い、同時に心の悩みまで真剣に聞き続けていては、いずれ心身が疲弊してしまいます。
頭では「聞き流せばいい」と分かっていても、困っている人を前にすると、つい真剣に聞き入ってしまうのが利佳子さんの性分なのです。
このお話から見えてくるのは、利佳子さんの「人の役に立ちたい」、「困っている人を何とかしたい」という気持ちが非常に強いということです。
そして、この「尽くしたい」という心理は、仕事だけでなくプライベートにも影響しているようでした。

2.恋愛における「尽くしすぎ」の傾向
利佳子さんはご自身の恋愛についても話してくれました。
「どうもだらしない男性を選んでしまうんです。今まで、水商売のような、いわゆる『いい加減な男』ばかりと付き合ってきました。友達からは『いい加減目を覚ませ』って言われるんですけど、普通の男性にはなぜか興味が持てなくて…」。
彼女は続けます。
「やっぱり、恋愛でも何かしてあげたい気持ちが強いんだと思います。周りからは『尽くしすぎ』って言われます」。
これは非常に重要な発言です。
仕事でもお客様に何かしてあげたい気持ちが強く、恋愛においても彼に何かしてあげたい気持ちが強い。まるで、誰に対しても、常に何かしてあげたいという気持ちが根底にあるかのようです。

そして、利佳子さんが惹かれるのは、彼女の言葉を借りれば「いい加減な男」。
つまり、「だらしない男」と言い換えてもいいかもしれません。
彼らがだらしないからこそ、「何かしてあげたい」という気持ちが芽生えるのでしょう。
利佳子さんは、そうした「いい加減な男性」を「困っている人」と捉えているように見受けられます。
逆に、しっかりしている男性に対しては、何かしてあげたいと思っても、実際に手助けする場面がないため、つまらないと感じてしまうのかもしれません。
しかし、彼女の恋愛はいつも同じ結末を迎えるといいます。
「たくさん何かをしてあげるんですけど、最後はいつも『うっとうしい』って言われてしまうんです。『俺はそんなこと望んでいない』とか、『いい加減に俺のこと分かれよ』って怒られることもあって…」。
この言葉から察するに、利佳子さんは「何かをしてあげたい」という気持ちから、一生懸命「だらしない男性」に尽くすものの、どうも相手が本当に求めていることとは違うことをしているようです。

a)「尽くす」行為の2つの側面
「尽くす」という行為には、大きく分けて2つの側面があります。
a)相手の望むことを察して先回りして行うこと。
b)相手の望むことよりも、自分ならこうしてもらえると嬉しいと思うことを行うこと。
どうやら利佳子さんは後者のタイプに当てはまるようです。
実際に、友人関係においても、相手が望まない(趣味ではない)本やDVDを「これいいよ!」と貸してあげて、友人から「やめてほしい」というメールが何度も来たことがあるといいます。
他者に何かをしてあげる時は、相手が何を求めているのかを理解することが非常に重要です。
自分が良いと思ったことでも、他者には興味がないことは多々あります。
他者にとって興味や価値のないことをどれだけしてあげても、それは自己満足の押し付けになりかねません。
結果として、相手にとっては迷惑になってしまうこともあるのです。

3.自己価値の確認としての「尽くす」行為
では、なぜ利佳子さんはここまで「自分にできることは何かしてあげたい」という気持ちが強いのでしょうか?
人の役に立ちたい、何かをしてあげたい、そして恋愛においては、普通の男性では何もしてあげることがないからつまらないと感じる。
ここまでの話から推測されるのは、利佳子さんが人に何かをしてあげることによって、自己価値を保っているのではないかということです。
裏を返せば、人に何もしてあげられない自分には価値がない、と感じてしまうのかもしれません。
この自己価値観の背景には、以下の2つのパターンが考えられます。

a)子ども時代の親の接し方の問題
親が子どもを褒めるのは、子どもが手伝いをしたり、親の役に立った時だけだったのかもしれません。そのため、子どもは「自分の存在を認めてもらうためには、何か役に立つことをしなければならない」と感じて育ち、大人になっても同じ行動を繰り返しているケースです。
b)見捨てられ不安が強い場合
他者から常に見捨てられるのではないかという不安が強い人は、他者に何かをすることで、その見返りとして「見捨てられない」という安心感を得ようとすることがあります。
利佳子さんの場合、どちらに当てはまるかは分かりませんが、カウンセリングなどを通して、もう少しご自身を見つめ直す必要があるでしょう。

4.「尽くしすぎ」がもたらす危険性
最後に、「相手に尽くしすぎる危険性」についてお伝えします。
ここでいう「尽くす」とは、相手のあらゆる要求や期待を満たそうとすることと定義します。
常に相手に尽くし続けると、相手は自分で何かをする必要がなくなり、楽を覚えます。
そして、尽くされ続けることで、自分ですべきことをしなくなり、何かをする機会を失い、そこから得られるはずの能力も育ちません。
結果として、尽くしすぎることは相手を無能化することにもつながるのです。

さらに、常に尽くされる状態が当たり前になると、尽くす側が少しでも手を抜いただけで、尽くされる側は「当たり前のことができていない」と感じ、激怒することさえあります。
皮肉なことに、「困っている人は放っておけない」と純粋な気持ちで何かをしてあげたいと思った相手によって、最終的に尽くす側が限界を超え、疲弊してしまうことがあるのです。