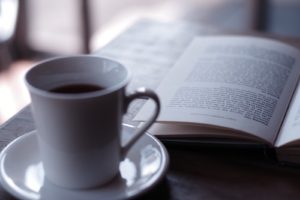要領の良い人は「ずる賢い」のか?〜取り組み姿勢と努力への評価〜
「要領が良い」って、どんなイメージですか?
「要領のよい人は得をする」。
この言葉、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
しかし、どこかネガティブな響きを感じ、「ずる賢い」「楽をしている」といった印象を抱く方もいるかもしれません。
例えば、社内において同期15名の中からAさんだけが早期に課長へ抜擢されたとしましょう。
同期の数人が「あいつは要領がいいからな」と陰口を叩く。
この言葉には、「要領が良い」ことを理由に、さも不当な評価を得たかのようなニュアンスが含まれているように感じられます。
では、そもそも「要領が良い」とは、どういうことなのでしょうか?

Index
1.国語辞典が示す「要領」の二面性
2.「ずる賢い」人は、結局は損をする
3.真の「要領の良さ」は、取り組み姿勢と努力の賜物
4.「要領の良い人」が評価される理由
1.国語辞典が示す「要領」の二面性
国語辞典で「要領」を調べると、主に2つの意味が記されています。
- 無駄がなく、手際よく物事をこなすこと
- 表面だけうまく見せかけ、実際には手を抜くこと
1の定義は、まさに効率的で望ましい能力を示しています。
一方、2は「ずる賢い」という、ネガティブなイメージを想起させます。
先ほどの例で同期がAさんを評した言葉は、この2の「ずる賢い」という側面に焦点を当てているように思えます。
しかし、本当に表面だけで手を抜く人間が、組織の中で正当に評価されるでしょうか?

2.「ずる賢い」人は、結局は損をする
「要領がいい」という言葉に「ずる賢さ」のイメージがつきまとうのは、「口先だけで、実際には何もしていない、あるいはできない」といった人物像を連想させるからかもしれません。
たしかに、「ずる賢い」人に対しては、初対面の人や事情を知らない人から見れば、巧みな話術や立ち回りに感心することもあるでしょう。
しかし、長く関わっていくうちに、その実態が伴わないことに周囲は気づきます。
上司、同僚、部下、様々な立場の人が見ている企業内では、表面的な「要領の良さ」はいつか見破られてしまうものです。
「ずる賢さ」は、遅かれ早かれ露呈し、人の信頼を失います。結果として、評価されることもなく、長期的に見れば、決して「得」をすることはありません。
むしろ、信頼を失うことの方が大きな損失となるでしょう

3.真の「要領の良さ」は、取り組み姿勢と努力の賜物
では、本当に「要領が良い」と評価される人は、どのような能力を持っているのでしょうか。前述の辞典の定義「無駄がなく、手際よく物事をこなす」を深掘りしてみましょう。
「無駄なく、物事をやってのける」ためには、以下のようなプロセスが考えられます。
a)情報収集と多角的な視点: 様々な選択肢や方法論を多角的に検討し、創造的に考える。
b)最適な選択と計画立案: 最適な方法を選び、具体的な計画を立てる。
c)柔軟な実行と修正: 目標に向かって計画に基づきつつも、状況に応じて臨機応変に修正を加えながら効率的に行動する。
d)責任感と強い意志: 目標達成のために、積極的に行動し、困難に直面しても諦めない強い意志を持つ。
e)成果の可視化と説得力: 達成した目標を成果として周囲に明確に示し、納得させるための説明能力。
このように考えると、「要領の良さ」とは、単なる口先のうまさではありません。
意思決定のための思考力、計画立案力、実行力、そして目標達成に向けた継続的な努力の積み重ねによって培われる能力と言えるでしょう。

「反射神経」と「即応力」も要領の良さに繋がる
さらに、「要領の良さ」は「反射神経」とも深く関連していると考えられます。
ここで言う反射神経とは、周囲の状況や出来事にいち早く気づき、適切に反応できる能力のことです。
具体的には、
- 周囲で何が起こっているのかを敏感に察知する洞察力
- その出来事に対し、自分がどう関わるべきか、どう動くべきかを瞬時に判断する思考力
- 判断に基づき、すぐさま行動に移せる実行力
これらの能力によって、迅速かつ的確に対応できる人は、周囲から「要領が良い」と評価される傾向にあります。
これは、決して「ずる賢さ」ではなく、優れた思考のスピードと的確な判断力の賜物なのです。

4.「要領の良い人」が評価される理由
結論として、「要領の良い人」とは、
a)仕事に対する積極的な取り組み姿勢
b)強い責任感に基づいた行動推進
c)目標達成に向けた継続的な努力
d)高い反射神経と、それに伴う思考力・行動力
これらを兼ね備え、実際に組織や業務に貢献し、成果を上げている人であると言えるでしょう。
「要領の良い人は得をする」という言葉は、しばしば嫉妬や妬みの感情を伴って語られることがあります。
しかし、実際には「得をしている」のではなく、その人の能力と貢献に見合った正当な評価を受けていると考えるのが適切ではないでしょうか。
あなたは、「要領が良い人」をどのように捉えますか?