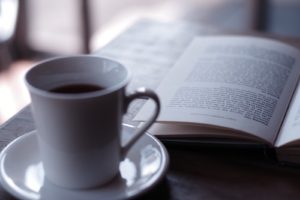期待と怒り、そして支配:その関係性を読み解く
誰もが経験する「期待」の落とし穴
私たちは日々、様々な人に対して「期待」を抱いています。
それは、親しい友人や家族、職場の同僚や上司、部下に至るまで多岐にわたるでしょう。
しかし、その期待が裏切られたと感じた時、私たちはどうでしょうか?
失望し、時には怒りを感じることも少なくありません。
なぜ人は他者に期待し、それが満たされないと怒りを感じてしまうのでしょうか。
その根底には、「期待」という名の「支配」が隠れているのかもしれません。

Index
1.「期待する人」の心に潜むもの
2.「期待される側」が持つ「選択権」
3.「期待」と「支配」と「怒り」の関係性
1.「期待する人」の心に潜むもの
人が他者に期待する心理的な動機は、主に3つあると考えられます。
a)「こうなってほしい」という純粋な願いの裏側
相手の幸せを願い、「こうなってほしい」と純粋に思う気持ちから生まれる期待は、一見すると「思いやり」のように感じられます。
もちろん、何を思い、何を期待するかは個人の自由です。
しかし、この「思いやり」からくる期待であっても、本当に期待された側がその期待を望んでいるのか、という視点が重要になります。
期待とは、期待する側と期待される側の二者関係です。
もし、双方の合意がなければ、期待する側の「期待」だけが一方的に先行してしまいます。
相手の気持ちや希望を十分に汲み取らないまま抱かれる期待は、時として、相手を自身の思い通りに動かしたいという「支配」へと繋がりかねません。

b)自分都合な「エゴ」と「欲求」がもたらす期待
「お金を貸してほしい」「恋人になってほしい」など、自分の都合や欲求を満たしたいがために、他者に期待するケースも少なくありません。
しかし、期待された側には、その期待を満たす義務は一切ありません。
このような一方的な期待は、時に相手にとって迷惑となり、応じる必要もないでしょう。
にもかかわらず、自分のエゴや欲求が強ければ強いほど、その期待感は高まります。
そして、相手に期待を断られると、激しい失望や怒りがこみ上げてくることがあります。
この失望と怒りは、まさに相手を自分の都合よく動かしたいという「支配性」の表れではないでしょうか。
理不尽な支配に基づく要求や期待に、進んで応じる人は少ないはずです。

c)組織における「役割」という名の期待
私たちは社会生活の中で、何らかの組織に属していることがほとんどです。
そして組織には目標があり、その達成のために構成員はそれぞれの役割を果たすことを期待されます。
例えば、会社において上司が部下に期待するケースです。
上司は部下を個人的に可愛がり、目をかけているつもりかもしれません。
しかし、部下には部下の能力の限界があり、上司の期待を完全に満たせないと判断することもあります。
また、部下自身の将来の目標が、上司の期待とは全く異なる方向性を示すこともあります。
このような状況で部下が上司の期待に沿うことを断り、退職を選ぶこともあるでしょう。
上司は「目をかけ、可愛がっていた部下に裏切られた」と失望し、怒りを感じるかもしれません。
しかし、ここにも「上司の期待を満たすべき」という暗黙の支配を感じます。
会社組織である以上、目標達成のために役割を果たすという考えは筋が通っていますが、その役割を受け入れるか否かの最終的な判断は、期待された個々人に委ねられています。
組織に属しているからといって、必ずしも組織の目標や役割に沿う必要はないのです。

2.「期待される側」が持つ「選択権」
期待する側の心理がいかなるものであっても、期待された側には常に「期待を受け入れる」、「期待を拒否する」、「期待を保留する」という3つの選択権があります。
期待した側は、相手が期待を満たせば満足するでしょう。
しかし、相手が期待を拒否したり、保留(考える時間の要求)したりすると、「期待外れだ」、「裏切られた」、「勝手な奴だ」といった感情を抱き、失望や怒りを感じることが多々あります。
しかし、そもそも期待するのは、期待する側の「勝手」なのです。
それが相手への思いやりから出たものであろうと、エゴや欲を満たすためであろうと、組織における役割期待であろうと、すべては一方的な期待に過ぎません。相手の都合を考えない、身勝手な期待も少なくありません。

したがって、期待された側は、その期待を拒否したり保留したりしても、全く問題ないのです。
もし、期待した人が、相手に「拒否」や「保留」を選択されたからといって怒ったとしたら、それは期待が満たされない失望感に加え、無意識のうちに「期待に沿ってほしい」、「期待を満たしてほしい」という「支配」が働いているからではないでしょうか。
いかに期待を抱こうとも、相手にはそれを受け入れるか否かの選択権があります。
相手から期待を拒否されたからといって怒ることは、相手の人権や選択権を尊重しない「支配性」の現れであると言えるでしょう。
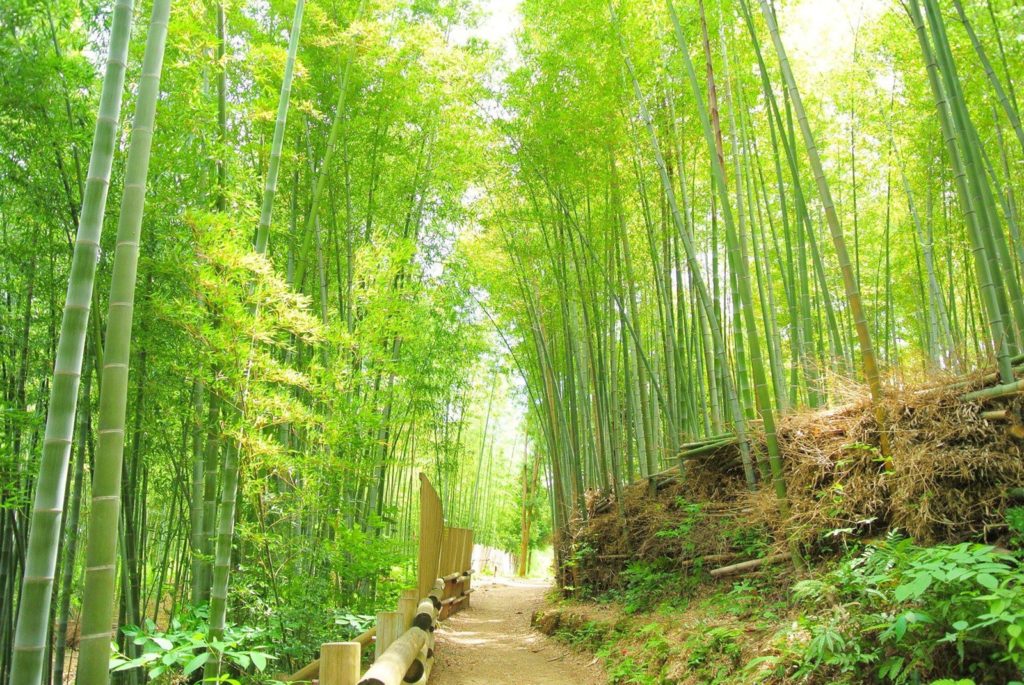
3.「期待」と「支配」と「怒り」の関係性
ここまでの話をまとめると、
a)期待すること:これは期待する人の自由であり、勝手です。
b)期待を受け入れるか否か:これは期待された側の選択権であり、自由です。
誰もが、期待した相手にはその期待を満たしてほしいと思うでしょう。
そして、相手がその期待を拒否した場合、期待が満たされないことへの失望を感じ、それが怒りへと転換されていくのです。
「期待を満たさないから怒る」という行動は、実のところ、相手の選択権や人権を軽んじた「支配」に他なりません。
期待を抱くこと自体は自由ですが、その期待の中に「支配性」が混じっていないか、注意が必要です。

期待と支配、そして支配の欲求が満たされないから失望し、怒る。期待とは、ともすれば身勝手な心理の傾向を持っているのです。
時には、期待を手放した方が心が楽になることもあります。
しかし、相手に全く期待しないことが人間関係の希薄さに繋がると感じるのであれば、期待したことに対して相手が拒否した時、相手の権利を尊重する姿勢が大切です。
もし期待を手放すことが腑に落ちないのであれば、「期待感を弱める」という考え方も良いでしょう。
いずれにせよ、「期待」という名の「支配」には、常に注意を払う必要があります。