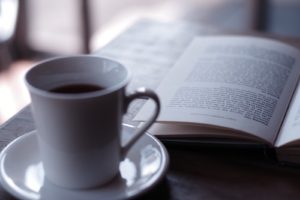買い物依存症の隠れた動機:孤独感と承認欲求が招く悪循環
「買い物依存」。
この言葉に、どれだけの人が悩みを抱えていることでしょう。
高価な品々や大量の買い物に走ってしまう買い物依存症の方々の心の中には、一体どのような思いがあるのでしょうか。今回は、私なりにその深層心理を掘り下げてみました。
買い物依存症に潜む様々な心理とは?

買い物依存症の方々の行動には、いくつかの心理的背景が考えられます。
1.「モノを持つこと」への満足感と優越感
高価な品や多くの「モノ」を手に入れることで得られる一時的な満足感や優越感があります。
「これだけ高価な品を、たくさん持っている自分」という感覚は、自己の価値を一時的に高め、心を一時的に満たします。
これは、自我拡大欲求を満たそうとする心理とも言えるでしょう
2.流行を追いかける高揚感と自己顕示欲
まだ誰も持っていない流行の最先端の品を手に入れることで、「自分は時代の先端を走っている」という高揚感を味わうことがあります。
奇抜なファッション、最新のゲーム、限定品など、その対象は様々ですが、「誰も持っていない特別なモノ」を持つことは、自己の特別感を刺激し、優越欲求を満たします。

3買い物時の「特別扱い」による満たされない心
買い物をする際、店員さんからの丁寧で特別な接客サービスに大きな満足を感じる方もいます。
「自分だけが特別に扱われている」という感覚や、長く続く心地よい会話は、孤独感を紛らわせる要因となることがあります。
しかし、これが行き過ぎると、不要なものを衝動的に購入し、買った商品を開封することなく山積みにしてしまったり、すぐに飽きて使わなくなったりと、無駄な出費につながることも少なくありません。

4.「寂しさ」ゆえに「騙されても」買ってしまう心理
以前、高齢者の方が訪問販売のセールスマンに「騙されていると分かっていながらも、あえて商品を買い続ける」という話を聞いたことがあります。
その根底には、「普段誰も訪ねてこないところに、たとえそれが嘘であっても、人が来てくれたら寂しい心が満たされる」という、深い孤独感がありました。
これは、買い物という行為が単に物品の購入だけでなく、人によってはコミュニケーションの場であり、人とのつながりを確認する場になっている可能性を示唆しています。

孤独と承認欲求が招く買い物依存症の事例
以下の事例はフィクションですが、買い物依存症の複雑な心理を理解する一助となるでしょう。
松代さん(仮名、50歳)は、食品製造工場でのライン作業に従事する、とても真面目そうな女性です。先日、多額の借金が原因で自己破産に至り、カウンセリングを受けにいらっしゃいました。いわゆる「買い物依存症」です。
現在、松代さんは一人暮らしで、結婚歴もなく、これといった趣味もありません。週末の唯一の楽しみは、バッグ、アクセサリー、服といった流行の高級ブランド品を購入することでした。
松代さんは、買い物をする動機について「自分には友達もいなくて孤独で、趣味もない。買い物が自分の孤独を紛らわせてくれる」と話されました。

当初、私は、買い物によって孤独を紛らわす行為は、「モノを集めることによる孤独からの逃避」だとイメージしました。つまり、孤独という心の隙間を、モノを集めることで一時的に満たそうとしているのではないか、と。これは、萎縮した自己を、モノを集めることで拡大しようとしている、とも言い換えられるでしょう。
松代さんのケースでは、高価なモノを集めることで、購入した商品の数だけ自分自身を満たしているのではないかと考えました。
さらに、もう一つの動機として、優越感に浸りたいという気持ちもあるのかもしれないと推測しました。流行の高級ブランド品を買い揃え、それを周囲に見せつけることで、知人であろうと見知らぬ人であろうと、誰かの注目を浴びて優越感に浸りたいという願望があるのでは、と。先ほどの心の隙間や萎縮した自己を、優越感によって満たそうとしているのではないか、と思ったのです。
しかし、カウンセリングを通して、ある大きな疑問が浮かび上がりました。それは、松代さんが商品を買った後、どうしているのか尋ねた時のことです。
彼女は言いました。「家には買った商品はありません。なぜなら、すぐにまた買い物をしなければならないからです。したがって、買った商品はすぐに質屋に持っていき換金して、また週末には別の店にブランド品を買いに行くんです。」
これは不思議な話です。
松代さんは、買ったモノで自分を満たすわけでも、身につけて見せびらかすわけでもないのです。
では、一体何を目的として、自己破産するまで買い物を続けたのでしょうか?

1.真の動機は「人間関係」と「承認欲求」への渇望
それは、やはり「孤独を紛らわすため」でした。
しかし、その方法は自己拡大や優越欲求によって孤独を満たすことではありませんでした。
松代さんには友人がいません。
仕事も食品工場でのライン作業で私語は厳禁。職場にも親しい人はいません。
したがって、今の生活では心を通わせる人が全くおらず、松代さん自身、社会との接点を感じにくい状態でした。また、「誰も自分を必要としてくれない、認めてくれない」という感覚さえ持っていたようです。
そこで彼女が思いついたのが「買い物」でした。それも、高価なブランド品の買い物です。
ブランド品は誰でも即断即決で買えるものではありません。そのため、ショップの店員との「商談」が不可欠になります。自分の要望を伝え、価格交渉などを行うだけでなく、それ以外の雑談も行われます。
ショップ店員からすれば、商品を売る話ばかりしていては、客との信頼関係が築けません。
当然、雑談を交えながら客の気を引き、同時に客に関する情報収集も行います。
松代さんは、まさにこのショップ店員との雑談を目的として買い物をしていたのでした。
松代さんは日常の生活空間において、話し相手が全くいない状態でした。人は生きていく上で、話し相手がいない孤独に耐えられるほど強い人は少なく、また、話し相手がいるということは、自己の存在を認知することにもつながります。

したがって、松代さんは客としてショップの店員と話しをすることで、人との交流を図り、自己存在の認知(承認欲求を満たす)を確認していたのです。店員であれば客を無視することもなく、むしろ愛想よく接してくれます。松代さん自身も、自分が客であるからこそ店員が相手をしてくれていることは十分分かっていました。
それでも、ショップ店員との関わりは、松代さんにとって欠かせないものだったのです。
それほどまでに、人との親交を求めていたのでした。
しかし、客といっても商品を購入せずに雑談ばかりしていると、いずれ店員から相手にされなくなることは明白です。また、自分の顔を覚えてもらい、いつでも丁寧に店員から接してもらうためには、定期的に店を訪れ、高額な商品を購入する必要がありました。
さらに、毎週同じ店ばかりに通っていては、お付き合いできる店員も限定されます。したがって、松代さんは高級ブランドショップを4店舗選び、月に1〜2回、交互に店舗を訪れ、ショップ店員との雑談を楽しみ、その雑談をするために高価な買い物を続けていたのでした。
松代さんは次のようにも語っています。「商品を買った後、店員さんがペコペコ頭を下げてくれるのは、たまらない優越感があった」と。
松代さんのケースは、確かに買い物依存ではありますが、モノを持つことによる心理的満足を得るのではなく、買い物を通した「人間関係」を求め、「自己存在の認知」や「承認欲求」を満たすことを目的とした、ショップ店員との「関係性への依存」だったのです。それが、店員と客という営利関係に基づく「偽の親交」であったとしても、松代さんは深く人との交流を求めていたのでした。

2.あなたの買い物行動、その本当の理由は?
もしあなたが、衝動的な買い物で悩んでいるとしたら、その背後にはどのような心理が隠れているでしょうか?今回ご紹介した事例のように、孤独感や承認欲求が関係しているかもしれません。
買い物依存は、単なる散財の問題だけでなく、心の奥底にある満たされない感情の表れであることが多くあります。
一人で抱え込まず、専門家に相談することで、その本当の動機と向き合い、健康的な心の状態を取り戻す一歩を踏み出すことができます。