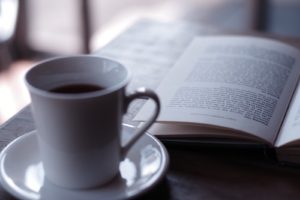転職回数が多い原因は「期待に応えられない自分は価値がない」という思い込みかも
化粧品販売員の樹里さん(仮名、32歳)が、退職と転職のご相談でカウンセリングにいらっしゃいました。
樹里さんは、人当たりの良いハキハキとした印象の女性です。
それだけに、なぜ退職を希望しているのか不思議に感じながらお話を伺っていたのですが、転職回数が5回もあると聞いて驚きました。
彼女の雰囲気からすると、人間関係もスムーズに築け、仕事もできる方だと感じたからです。短大卒業後12年で5回も転職されているとは、正直なところ信じられませんでした。
「周囲の期待に応えられないと価値がない」という思い込み
Index
1.昇格後の責任を果たす自信がなく退職を決意
2.自分はできない人間であり、期待に応えられないことに周りは失望するだろう
3.子どもの頃の「母の期待に応えられない自分は価値がない」という思い込み
4.子どもの頃の思い込みの延長、「人は私にすべて一人ですることを期待している」
1.昇格後の責任を果たす自信がなく退職を決意
今回の退職理由は、来月、店長への昇格が決まったにもかかわらず、その責任を果たす自信がないため、もっと責任の軽い仕事への転職を希望されているとのことでした(具体的には、指示されたことをこなすタイプの仕事を希望されていました)。
さらに、これまでの退職理由を伺うと、すべてが部署異動や配置転換、昇格など、新しい仕事へのチャレンジが巡ってきたタイミングで、すぐに退職を決意されていたのです。
通常、職場での新しい配置転換は、これまでの努力が評価され、次のステップに進むチャンスと捉えられます。
そこには職位の昇格が伴うこともあり、仕事に対する責任は増えますが、同時に新しいやりがいを見つけられる機会でもあるはずです。

樹里さんに、なぜいつも新しいチャンスが巡ってくるたびに退職してしまうのか尋ねると、「新しい仕事や責任を果たすことに自信がないから」という答えが返ってきました。
確かに、今までとは違う仕事を任されるのですから、不安があるのは当然です。
しかし、新しい仕事の責任を果たせるかどうかは、実際にチャレンジしてみないと分からないものです。
また、樹里さんは人当たりの良い雰囲気の方です。
その雰囲気からすると、社内では先輩からのサポートも十分に受けられるように思えました。
昇格したとしても、不安なことを一人で抱え込まず、上司や先輩に助けてもらえばいいのではないでしょうか。
この点を樹里さんに指摘したところ、彼女はこう答えました。

「今まで、できるだけ人を頼らず仕事をしてきました。人に頼ることは、自分が仕事ができないことを周囲に知られることにつながるので、人に助けを求めることはできないのです」
さらに、彼女はこう続けました。
「人に頼って周囲を失望させたくないのです」
ここまで聞いて、樹里さんが何を思っているのか、おぼろげながら理解できるようになりました。

2.自分はできない人間であり、期待に応えられないことに周りは失望するだろう
樹里さんの心の中には、このような思考の道筋があるように感じられました
①:分からないことを人に聞くことは、自分ができない人間であることを証明することになる。
②:そして、人から期待された時に、その期待に応えられない自分に周囲は失望するだろう。
③:だから、仕事は与えられたことをこなす自己完結型の仕事が希望である。
④:そして、仕事について相談して失望されるのが恐ろしく、責任の重い新しい仕事に就く前にやめてしまう。
⑤:退職すれば、周囲は私ができない人間であることを知ることはない。誰も私に失望しない。
この道筋で、樹里さんはこれまで動いてきたように思われます。
しかし、なぜ彼女は、自分が分からないことを人に聞いたり相談したりすると、「自分はできない人間であり、周囲は樹里さんに失望する」と思い込んでいるのでしょうか。
彼女は、子どもの頃のことを次のように話しています。

3.子どもの頃の「母の期待に応えられない自分は価値がない」という思い込み
「私は母子家庭でした。母は常に忙しく、私は常に母の手間を取らないように気をつけていました。でも、何でも一人でできるわけではなく、母の手を何度も煩わせてしまいました。母の手を煩わせるたびに、『自分なんて、ダメだ』と思いました」。
樹里さんは子どもの頃、忙しいお母さんの手を煩わせたくなかったのです。
お母さんは樹里さんのために手を止めても、怒ったりすることはなく優しく接してくれていたようですが、樹里さんは子どもながらに母に気を遣い、「何でも自分一人でしなければならない」という思い込みを勝手に抱きました。
そして、それができない自分に母は失望していると、できない自分の罪悪感を「母が自分に失望している」と置き換えてしまったのでしょう。
(これは心理学でいう投影の心理です)。

4.子どもの頃の思い込みの延長、「人は私にすべて一人ですることを期待している」
樹里さんの「期待に応えられない自分は価値がない」という思い込みの原点は、ここにありました。
(「母は樹里さんが何事も一人ですることを期待している。その母の期待に応えられない自分は価値がない」という思い込み)。
そして、今もその思い込みを持ち続けているのです。
さらに、「自分に対しては、何事も一人で責任を持ち行動しなければならない。したがって、周囲に頼ってはいけない」と、様々な思い込みに縛られていたのでした。
樹里さんが今後、退職を繰り返さず、ご自身のキャリアを築いていくためには、まずこの「思い込み」がどのように形成されたのかを理解し、その思い込みを手放すことが重要です。

そして、新しい仕事に臨み、分からないことは分からないと周囲に助けを求め、その結果何が起こるのかを実際に体感することが必要です。
私たちの人生や自分に対する思い込みは、親の言葉をそのまま受け入れて苦しむ場合もあれば、樹里さんのように、子どもの頃に親に気を遣い、親に対する罪悪感から思い込みを背負ってしまう場合もあります。
このような思い込みについて深く考え、過去を振り返るには、心理カウンセリングが非常に有効な手助けとなるでしょう。