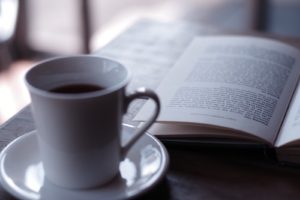人を悪く決めつける心理:その奥にあるものは何か
誰かのことを「この人はこういう人だ」と決めつけてしまう。私たちは日常生活の中で、こうした判断を無意識のうちに行っていることがあります。
ここで言う「悪く決めつける」とは、相手の事情や人柄、能力についてよく知らないにもかかわらず、自分の主観や思い込みだけで相手を自分より下に見たり、軽んじたりする心理や態度を指します。
では、なぜ私たちは、このように他者を軽蔑したり、見下したりするような評価をしてしまうのでしょうか。
その背景にある心理を4つのポイントで見ていきましょう。
人を悪く決めつけてしまう4つの心理的要因
Index
1.対話不足が生む「勝手な推測」
2.「見た目」が引き起こす最初の思い込み
3.許容できない「価値観の相違」
4.劣等感から生まれる「嫌悪感・嫉妬・敵意」
5.誰かを決めつける前に、できること
1.対話不足が生む「勝手な推測」
人を悪く決めつける大きな要因の一つに、対話不足があります。
相手と十分に話す機会がないまま、自分の想像だけでその人の性格や能力を判断してしまうケースは少なくありません。
しかし、そもそもなぜ対話が生まれないのでしょうか?
それは、相手に対してすでに何らかのネガティブな感情を抱いているからです。
「話したくない」、「関わりたくない」という気持ちが先行し、コミュニケーションを避けてしまう。
そしてそのネガティブな気持ちが、さらに相手への軽蔑や侮蔑へとつながっていくのです。

2.「見た目」が引き起こす最初の思い込み
私たちは、初めて会う人の見た目や話し方、振る舞いから、一瞬でその人の印象を決めつけてしまいがちです。
特に、この最初の印象がネガティブなものだった場合、その後の評価を覆すことは非常に難しくなります。
「この人はなんだか感じが悪いな」、「きっとこういうタイプの人だ」といった主観的な思い込みが、相手を悪く決めつける原因となります。
もちろん、初対面の人を否定的に判断する傾向は、自己防衛本能の一種とも考えられます。
「この人は自分にとって危険な存在ではないか」と、無意識のうちに安全性を確認しようとする心理が働くからです。
しかし、その多くは単なる思い込みに過ぎない可能性が高いのです。

3.許容できない「価値観の相違」
たとえ対話の機会があったとしても、相手との価値観の違いがあまりにも大きいと、「分かり合えない」と感じることがあります。
「違いは違いであり、間違いではない」と頭ではわかっていても、自分の価値観と合わない相手に対してネガティブな感情を抱いてしまうのは、人間としてごく自然なことです。
しかし、そこで相手を「間違っている」と決めつけ、見下してしまうと、関係はさらに悪化します。
多様な価値観を認める寛容性と、自分と異なる考え方を客観的に受け入れる姿勢があれば、「分かり合えなくても、そういう考え方もある」と割り切り、不必要な対立を避けることができるはずです。

4.劣等感から生まれる「嫌悪感・嫉妬・敵意」
相手に対する嫌悪感が強いと、根拠もなくネガティブな評価をしてしまいがちです。
その嫌悪感は、価値観やフィーリングの違いだけでなく、実は自分自身の劣等感からきている場合があります。
特に、自分より優秀な人を見たとき、素直に認められず、嫉妬心が芽生えることがあります。
そして、その嫉妬心から相手の欠点ばかりに目がいき、「あの人は〇〇な人だ」と悪い方に決めつけてしまうのです。
これは、相手を悪く評価することで自分の優越性を保ち、心のバランスを取ろうとする心理の表れです。

5.誰かを決めつける前に、できること
私たちは、誰かを悪く決めつけそうになったとき、一度立ち止まって考えてみることが大切です。
その決めつけは、本当に相手の事実に基づいているでしょうか?
それとも、自分自身の対話不足、思い込み、価値観の違い、あるいは劣等感から生まれているものではないでしょうか?
もし、その原因が自分自身にあると感じたなら、相手を悪く決めつける前に、自分自身の心を見つめ直すことが問題解決の第一歩となります。
最後に、もし誰かのことをネガティブに決めつけてしまっても、それを周囲に吹聴しないよう注意しましょう。
他人の評価は人それぞれです。あなたの決めつけが悪口として広まることで、結果的にあなた自身の人間性や評価が下がってしまう可能性もあるからです。
「決めつける」という思考や感情を完全にコントロールすることは難しいかもしれません。しかし、「それを口に出すか出さないか」という行動は、自分の意思でコントロールできるのです。