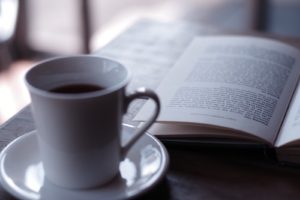怒らないのか・怒れないのか【怒りを表現できない心理】
この世に怒りを感じたことがない人は、おそらく一人もいないでしょう。何
に怒りを感じるかは人それぞれですが、その怒りの感情をどう扱うかは、その人の生き方や置かれた状況によって大きく変わってきます。
今回は、誰かから向けられた言動や態度によって生じる怒りをテーマに、「なぜ怒りを表現できないのか」という心の奥底にある心理を、5つのタイプに分けて掘り下げていきます。
サブタイトル:怒りを表現できない心理と、そこから生まれる問題
Index
1. 怒りを「いけないもの」だと教えられてきた
2.怒りを表現して「嫌われる」のが怖い
3.怒った後の「不利益」を計算してしまう
4.怒りで「理性を失う」のが怖い
5.全く関係ない人に怒りをぶつけてしまう

1. 怒りを「いけないもの」だと教えられてきた
怒りという感情を表現することに、強いブレーキがかかってしまう人がいます。
それは、「怒り方を知らない」、「怒りは我慢するものだ」、「価値のない自分は怒ってはいけない」といった、過去の経験からくる思い込みが根底にあるかもしれません。
どれだけ「怒らない」と心に決めていても、不当な扱いに怒りが湧くことはあります。
しかし、その怒りを「自分が悪いからだ」と自分の責任にしてしまう。
これは、健全な自己愛が育まれていない、自分を大切にできていない心理の表れです。
こうした傾向は、育った環境、特に親との関係が大きく影響していると考えられます。
子どもの頃、親の力が強すぎると、子どもは自分を否定的に捉え、怒りを感じても表現することを抑え込む「自己抑圧型」の人間になってしまうことがあります。

本来であれば、親や周囲との関わりの中で、健全な怒りの表現方法を学びます。
しかし、それができなかった場合、大人になっても怒りを我慢し続け、ついには「怒り」という感情自体がわからなくなってしまうことも。
怒りは誰でも感じる自然な感情です。
その感情を心の中に溜め込みすぎると、社会生活に支障をきたしたり、そのエネルギーが自分自身を傷つける方向に向かい、心の病につながる可能性も否定できません。

2.怒りを表現して「嫌われる」のが怖い
現代を生きる私たちは、人から嫌われることへの恐れが過剰なほど強くなりがちです。
特に、親しい人との関係では、「もし不満を伝えたら嫌われてしまうかもしれない」と、怒りを我慢してしまうことが多いのではないでしょうか。
本当に、親しい人との関係は、少し怒りを表現しただけで壊れてしまうほど脆いものなのでしょうか。
親しい人に怒りを感じたということは、相手の言動によってあなたの心が傷ついた証拠です。
その怒りを無視して、何事もなかったかのように付き合いを続けることは、自分の心をないがしろにすることに他なりません。
嫌われることを恐れて自分ばかりが我慢する関係は、やがて不平等になり、いずれ破綻してしまうでしょう。

親しい相手だからこそ、まずは穏やかに「今、こういうことで悲しい(または不快だ)と感じている」と伝えてみることが大切です。
それによって、相手も自分の真意を伝えたり、お互いの理解が深まるきっかけになるかもしれません。
もし、穏やかに伝えても相手が怒り出し、あなたの気持ちをまったく理解しようとしないのであれば、その人との関係を本当に続ける必要があるのか、一度立ち止まって考えてみてもいいのではないでしょうか。

3.怒った後の「不利益」を計算してしまう
職場やコミュニティなど、集団の中で心を傷つけられるような言動があったとき、怒りを感じても、あえて怒りを表現しない選択をすることがあります。
これは、怒りをぶつけた後に生じる周囲からの不利益や、自分の居場所がなくなることを恐れてのことでしょう。
人間は社会的な生き物ですから、集団の中での自分の立ち位置を考えて、怒りを表現するかどうか決めるのは賢明な判断です。
組織や集団は継続的な場所だからこそ、怒りを表現した後のことをよく考える必要があります。
そして、怒りを我慢し、受け入れるしかない場面もあるかもしれません。
しかし、もし可能であれば、個人的に話し合いの場を設けて、お互いの主張や思いを伝え合うことが解決策につながる場合もあります。
とはいえ、人の話を聞く耳を持たない人が一定数いるのも事実です。
理不尽ではありますが、社会生活を送る上では、怒りの感情を抑えることが必要なときもあるのです。

4.怒りで「理性を失う」のが怖い
激しい怒りの感情とともに、自分が理性を失い、非理性的な行動をとってしまうことを恐れ、怒らない選択をする人もいます。
怒りに飲み込まれ、相手を破壊したいほどの衝動に駆られたり、暴言を吐き続けて相手を追い詰めてしまう経験があるのかもしれません。
怒りを感じると、自分のコントロールが効かなくなり、相手を傷つけてしまうことを恐れているのです。これは、生まれ持った気質が影響している可能性もあります。
このような傾向がある方は、まずは日頃から穏やかに過ごすことを意識してみましょう。
スポーツなどで体を動かし、エネルギーを発散したり、瞑想や深い呼吸を意識してリラックスする時間をとるのも良い方法です。
また、些細なことでも怒りを感じてしまうことがあるなら、その都度怒りの感情を適度に受け流す練習をしてみるのも有効です。
心理カウンセリングにおいて、上手な怒りの感情の受け流し方を考えることも念頭に置いて良いでしょう。

5.全く関係ない人に怒りをぶつけてしまう
怒りは破壊的なエネルギーであり、溜め込みすぎると心身に悪影響を及ぼします。
健全な方法で怒りを表現し、ストレスを発散することは、心を健康に保つために必要なことです。
しかし、その怒りの矛先を、原因を作った当人ではなく、全く関係のない人に向けたりするのは健全な方法とは言えません。
本来向き合うべき相手に怒りを表現できないため、自分より弱いと思う人に怒りをぶつけてしまう。
これは「いじめ」につながる行為です。
また、職場で受けた怒りを家庭で家族にぶつける「八つ当たり」は、家族関係の悪化を招きます。
さらに、SNSの普及した現代では、関係のない第三者に対して誹謗中傷という形で怒りを発散するケースも見られます。
しかし、このような行為は問題を解決するどころか、自分の人間性を疑われるだけでなく、新たな問題を引き起こすだけです。

怒らないことが、本当にあなたの幸せにつながっていますか?
怒れない自分を変える第一歩は、「健全な怒りの表現方法を学ぶ」ことです。