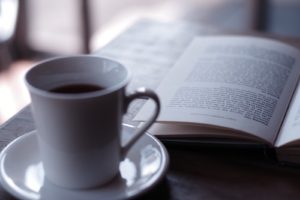退職に対する「説明責任」を果たす重要性と退職を阻止する企業への対応
私たちは日々の仕事において、多くの場合、企業や団体、施設などに雇用され、その指示のもとで業務に励んでいます。
どのような仕事に就いているかは人それぞれですが、もし仕事内容が自分に合っていて、職場環境も良好で、人間関係にも問題がなければ、仕事に専念でき、日々充実感を味わえることでしょう。
しかし、もし仕事が自分に合わない、職場環境や人間関係に多大なストレスを感じるなど、さまざまな問題に直面した時、人は退職という選択肢を考えるかもしれません。
無理をして働き続け、心身を壊してしまうのであれば、退職することもまた賢明な選択と言えるでしょう。

退職の意思を伝えるということ:説明責任と、それを阻む会社の壁
Index
1.退職の意思表示:あなたの人間性が問われる時
2.退職を妨げようとする会社との向き合い方:あなたの権利を行使する時

1.退職の意思表示:あなたの人間性が問われる時
さて、退職を決意した時、その思いや事情を上司に説明することは不可避です(もちろん、黙って出社しなくなるという選択肢もありますが、それでは保険や年金、失業給付などの行政手続きが滞り、あなた自身が不利益を被る可能性があります)。
したがって、退職時には何らかの形で「辞めます」と明確に伝える必要があります。
そして、その一言を伝えるためには、多くの場合、会社の上司に直接話し、退職に至った経緯やご自身の思いを伝えることになるでしょう。
話しにくいデリケートな内容だけに、気が重いと感じる方も少なくないはずです。
しかし、これはこれまでお世話になった会社に対する、最低限の義務的な行為であり、人としての礼儀でもあると私は考えます。

もしこの「退職したい」という意思を、自分の口で伝えることができず、何も言わずに連絡を絶ってしまうような形で会社を去ってしまえば、後になって後悔の念に駆られたり、ご自身の自信や自己肯定感の低下、あるいは罪悪感を抱き続けて生きることに繋がってしまうかもしれません。
退職時のことを思い出すたびに、ずっと後悔し続ける人生は、やはり辛いものです。
だからこそ、やはりお世話になった会社には、きちんと退職の意思を伝える「説明責任」を果たすべきなのです。
退職を決めた際は、上司と面談の場を設け、ご自身の言葉でしっかりと話をするのが望ましいでしょう。

2.退職を妨げようとする会社との向き合い方:あなたの権利を行使する時
しかし、この「退職を伝える」という行為は、同時に不安やリスクを伴うものでもあります。
なぜなら、「退職します」と口にした途端、上司が怒鳴りつけるようなパワハラに発展したり、「辞められたら人手不足で仕事が回らない」、「辞めないでくれ」と泣き落としをされるなど、退職を妨げようとする言動が待っているかもしれないからです。
想像するだけでも、不安は高まりますよね。

しかし、そこで最も大切なことは、ご自身の退職の意思を口頭で明確に伝えることです。
もし、そのような厄介な上司や会社であるならば、ご自身の身を守るためにも、胸元にレコーダーを忍ばせ、全ての会話を録音することも大切な自己防衛策となりえます。
なぜなら、私たちには仕事を選ぶ権利、そして会社を辞める権利が明確に認められているからです。
また、企業や会社も景気の変動によっては、当然のように社員を解雇することがあります。
労働者と会社は本来、対等な関係であるべきではないでしょうか。
それを「辞めさせない」と一方的に言うことは、会社の都合による人権侵害とさえ言えるでしょう。
もしそのような状況に陥った場合は、証拠となる録音内容を手に、弁護士に相談することも一つの有効な手段です。
多少の費用はかかるかもしれませんが、あなたの権利を守るためには必要な投資となりえます。

つまり、お世話になった会社(入社時の経緯がどうであれ)を辞めるのであれば、まずは上司などに相談し、ご自身の意思を伝えてください。
もし上司や会社が正当な理由なく退職を認めないというのであれば、これを人権侵害と捉え、弁護士など専門家の介入を検討しても良いでしょう。
問題の多い会社が存在することは事実です。
しかし、あなたが連絡なしに会社に行かないという選択をすれば、あなた自身が不利益を被る可能性が高まります。きちんと手続きを踏んで退職できれば、あなた自身の自信や自己肯定感、自尊心はダメージを受けずに済みます。
それどころか、「逃げずに最後までやり遂げた」と、ご自身で自分を褒めることにも繋がり、結果的に自信や自己肯定感、自尊心を高めることにも繋がるのではないでしょうか。

退職は大きな決断であり、時には困難を伴うものです。
しかし、そのプロセスを適切に進めることは、あなたの次のステップへの大切な準備であり、何よりあなたの人間性を育む機会となるのではないでしょうか。