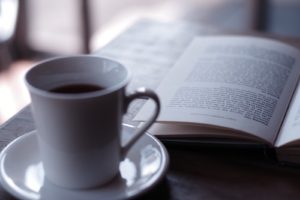繊細な人が社会で輝くために【生きづらさを強みに変える】
はじめに。
この記事で使う「社会環境適応力」という言葉は、主に「人間関係を築き、維持していく力」という意味で書かせていただいております。
ご了承ください。

繊細さと社会環境適応力の関係
Index
1.繊細さの感受性
2.繊細さは「柔」の力
3.「過剰」を「適切」に変える
4.居心地の良い場所を見つける冒険
1.繊細さの感受性
繊細な人、いわゆるHSP(Highly Sensitive Person)は、次のような特徴を持つことが多いです。
- 相手が感じていることや、自分に対する思いがなんとなく伝わってくる
- 大きな音や、ざわざわした雰囲気が苦手
- 心配性で、不安を感じやすい
このように「繊細さ」にはさまざまな形がありますが、共通しているのは、あらゆる刺激に強く反応する、高い感受性を持っていることです。
このような繊細さと、社会環境適応力には関連性があるのでしょうか?
私の結論から言うと、繊細すぎるがゆえに、社会環境への適応に難しさを感じることはあると考えます。

さて、繊細さの反対に「鈍感力」という言葉があります。
鈍感な人は、物事を深く悩みすぎず、楽観的で、人間関係や環境の問題で悩むことが少ない傾向にあります。
そのため、社会環境への適応力も高く、生きやすいと感じている人が多いかもしれません。
しかし、行き過ぎた鈍感さは、他者の心を理解できず、自分中心な振る舞いにつながるため、注意が必要です。

2.繊細さは「柔」の力
繊細な人は、相手の気持ちが分かりすぎるがゆえに人間関係で苦労したり、過剰に気を遣いすぎて自己主張できなかったりすることがあります。
また、さまざまな刺激に過敏に反応してしまうつらさも抱えているでしょう。
実は、私自身も繊細な一面があり、特に聴覚過敏があるため、人混みのざわざわした雰囲気が苦手です。だからこそ、繊細な人が感じる生きづらさはよく理解できます。
しかし、繊細さとは、鈍感力とは真逆の力であると同時に、何らかの才能の土台にもなるのではないでしょうか。
鈍感を「剛(ごう)」の力と捉えるなら、繊細さは「柔(じゅう)」の力です。

柔とは、柔軟でしなやかな枝のような力です。
強い風にも折れず、風の流れを受け流しながら、内なる強さを発揮することができます。
繊細な人が鈍感になることはできません。
それは、柔が剛にはなれないのと同じです。
しかし、過剰な反応(過敏さ)を弱めることはできます。
そして、繊細な自分を好きになれる日がきっと来るはずです。

3.「過剰」を「適切」に変える
ここからは、繊細さにおける人間関係の適応力についてお話しします。
繊細な人は、相手の気持ちに寄り添い、じっくりと話を聞くのが得意です。
この才能によって、多くの人から感謝されることがあるでしょう。
しかし、その才能が「過剰」になってしまうことがあります。
- 相手の話を聞き続けないと嫌われるのではないかと、無理をしてしまう
- 話を聞くのがつらくなっても、やめられない
- 結果的に人と接すること自体が嫌になり、自分を嫌悪してしまう
このように、繊細さの問題は「過剰」な反応にあります。
バランスが崩れてしまうのです。
では、この「過剰」をどうすればいいのでしょうか。
心理カウンセリングなどを通じて、自身の繊細さや過敏さに対する対処法を学ぶことで、「過剰」な反応を抑え、バランスの取れた「適切(適度)」な対応ができるようになります。
そうなれば、自己嫌悪や自己否定が弱まり、自己肯定感や自信を高めることもできるでしょう。

4.居心地の良い場所を見つける冒険
繊細な人は、自分の強みである繊細さを活かしながら、社会に適応して生き抜くことができます。
それでも、どうしても今の環境に居心地の悪さを感じてしまう場合は、自分に合った社会環境を探すことも大切な選択肢です。
それは、心地良い居場所を探すための冒険と言えるでしょう。
繊細な人は、未来への不安から冒険を好まないかもしれません。
しかし、「置かれた場所で咲く」のではなく、「自分が花を咲かせられる場所を探す」ことも大切なのです。
繊細さという天賦の才を信じ、どうか前向きに進んでいってください。