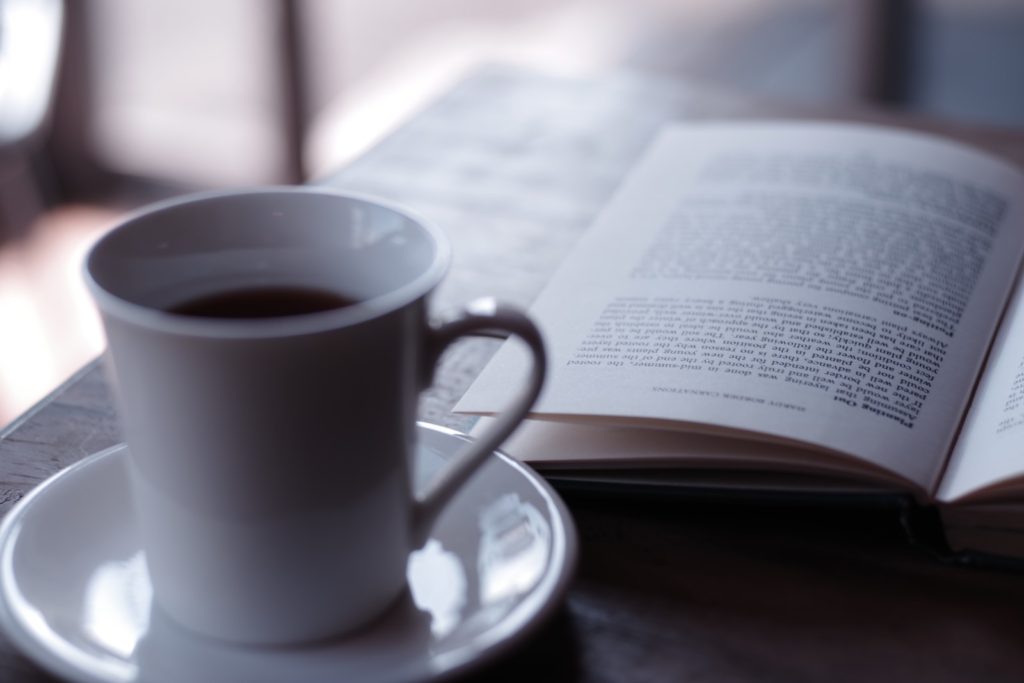心理 心理学 カウンセラーの考え– category –
-

AIに「寄り添い」を求める心、その裏にあるもの
なぜ私たちは、ChatGPTとの会話に安らぎを感じてしまうのか? 私たちは、誰かに自分のことをわかってほしい、共感してほしい、ただそばにいてほしい、そう願う生き物なのかもしれません。 今、多くの人が利用しているChatGPT。そのAIに、まるで人間のよう... -

『皆』という強い言葉の力と無意味さと恐ろしさ
「皆がそう言っている」、「皆と同じようにしなさい」。私たちは日常的に「皆」という言葉を使います。 この一見無害な言葉の裏には、個人の自由を抑圧し、他者を排除するほどの強い力が潜んでいることをご存知でしょうか? 心理カウンセリングの現場でも... -

癒しを目的とするカウンセリングに対する違和感
カウンセリングにおいて、癒しを目的とすることは、目標設定上、妥当なことなのでしょうか。 また、カウンセリングにおける癒しとは、どのような状態のものを指すのでしょうか。 https://youtu.be/n9mXkUKLZU0 カウンセリングにおける癒しは必然ではなく偶... -

真面目さにおける不安と自己防衛の心理
真面目。真面目とは人の基本であり、ずっと真面目さを維持することは、以外と難しいと考えます。 なぜなら、人の心の中には怠惰な部分もあり、また、外に目を向けると誘惑と刺激も多い。真面目とは、これらと戦って維持されるものなのです。 さて、真面目... -

ワンナイトラブによる異性から求められる自己承認の脆さ
ワンナイトラブによる自己承認とは 先日、テレビ番組で「ワンナイトラブ」を繰り返す女性のインタビューを目にする機会がありました。彼女は、その理由を「自己の承認を満たすため」だと語っていました。 この言葉に、違和感を覚えた方もいるかもしれませ... -

社会不適応とは何を意味しているのか?
「社会に適応していない」。 「社会不適応」。 これらの言葉をよく耳にします。 社会不適応。 この言葉を考えるのに大切なことは、「社会」とは、何かということです。 社会。 一般的には、私たちの属している社会。家、家庭以外において、何らかの活動を... -

べき論(人はなぜ自分にべき論を課すのか・そして恐れ)
自分に課した「べき論」の正体と、その手放し方 「〜すべき」、「〜でなければならない」といった「べき論」に、生きづらさを感じている方は少なくありません。 適切な「べき論」は、私たちの生活に秩序をもたらし、目標に向かう原動力にもなります。 しか... -

カウンセリングの対話がストップする、その隠れた理由とは?
心理カウンセリングは、相談者様とカウンセラーが1対1で言葉を交わし、抱えているお悩みの解決を目指すプロセスです。 しかし、時にこの対話がぎこちなくなったり、進まなくなったりすることがあります。うなってしまうと、カウンセリング本来の力を発揮で... -

自立と自律の関係性:より良い人生を歩むために
私たちは皆、「自分の足で立ちたい」と願い、また「社会の中で穏やかに生きていきたい」と願っています。 その中で、「自立」と「自律」という言葉がしばしば用いられますが、これらの意味や、私たちの人生における重要性については、深く考える機会は少な... -

自分の悩みが一番辛いと思わないこと?皆苦しみと悩みを抱えている
私たちは皆、それぞれの人生の中で様々な悩みを抱え、苦しんでいます。その悩みは、原因によって大きく分類できます。例えば、 アダルトチルドレンとして、過去の家族関係に起因する生きづらさを抱える方 家族の介護や世話を担うヤングケアラーとして、自... -

配慮心と譲る心:なぜ「譲れない人」が増えているのか?
公共の場で、席を譲るべき場面でスマホに夢中になっている人、急いでいるからと列に割り込もうとする人。そんな光景を目にするたびに、「なぜ、この人は譲らないのだろう?」と疑問に感じたことはありませんか? 昔はもっと「譲り合い」の精神が当たり前だ... -

愛を説く人は本当に愛を知っているのか
愛とは説くものではない。愛、それは、行為行動より示されるものではないでしょうか。 https://youtu.be/qfR385whXW8 私は愛とは行動行為(思いやりに満ちた言語表現等含む)の中に見出すものであり、愛とは何か説くものではないと考えます。 さて、言葉の... -

心理カウンセリングにAIは役立つのか?その可能性と限界
近年、AI(人工知能)の進化は目覚ましく、様々な分野でその活用が期待されています。では、私たちの心に寄り添う心理カウンセリングにおいて、AIはどのような役割を担えるのでしょうか? AIがカウンセリングの現場で活躍する可能性と、その限界について、... -

容姿(顔・スタイル)を変えて自信をつける:内面と外面の相乗効果
「自分に自信がない」というお悩みは、心理カウンセリングの現場で多くの方から寄せられる相談内容の一つです。自信を育むためには、新たな挑戦、成功体験の積み重ね、自己否定の止めるなど、思考レベルから感覚レベルまで、内面の健全な循環を促すアプロ... -

精神科・心療内科の受診、ためらっていませんか?
精神科・心療内科での治療をためらう心理 Index1.副作用と薬漬けの不安2.「薬漬け」への不安と医師とのコミュニケーション3.精神科・心療内科医との「相性」4.精神科・心療内科と心理カウンセリングの違い、そして併用の可能性 1.副作用と薬漬けの不安 心... -

路上で子どもがたばこを吸う心理:私たちはどう向き合うべきか
先日、商店街を歩いていると、小学生高学年くらいの少年が、あたりまえのようにたばこを吸いながら歩いているのを見かけました。周囲の大人は誰も注意することなく、私もまた、ちらりと彼を見ただけで、その場を通り過ぎてしまいました。 https://youtu.be... -

承認欲求|自己存在の承認と心の満足
自分が承認される大切さ:人は承認を求めて生きる 私たちは皆、「自分を認めてほしい」という気持ちを心の奥底に持っています。 これは、他者から認められることで、自分の存在を肯定したいという、人としてごく自然な欲求です。この欲求が満たされること... -

憎しみは人間の本質|憎しみは愛と表裏一体ではない
「人を憎んではいけない」、「許しなさい」。私たちはそう教わってきました。しかし、憎しみという感情は、本当にいけないものなのでしょうか。 私は、憎しみは人間が本質的に持っている感情の一つだと考えています。 なぜなら、私たちは他者に対しては強... -

お金がないと「生きる意味を見失う」のは当然のことと考えます
お金・収入がないと生きていくのが難しい現実について 私たちは、生きていく上で、お金がなければ食べることも、住むことも難しい現実を日々感じています。それでも、「お金がなくても、生きる意味はある」、「希望は必ず見つかる」といった言葉を耳にする... -

行き過ぎた個人主義は「利己主義」となるのか
行き過ぎた個人主義と集団主義について考える 私たちは、コロナ禍において、さまざまな価値観のぶつかり合いを目の当たりにしてきました。特に、欧米で見られた「個人の自由」を主張する人々の行動は、多くの日本人に違和感を与えたのではないでしょうか。... -

対人援助職が陥りやすい「見えない落とし穴」とは?
対人援助職や支援員として、日々多くの相談者と向き合う中で、「良かれと思ってやったことが、かえって裏目に出てしまった…」と感じることはありませんか? 真摯に取り組んでいるからこそ陥りやすい、いくつかの心理的な罠と問題点についてお話しします。 ... -

コミュニケーション障害?「コミュ障」はあなたの個性かもしれない
「コミュ障」と決めつけない大切さ:それは唯一無二の個性です 「もしかして、自分はコミュニケーション障害(コミュ障)なのかな?」そう悩んだことはありませんか? 大勢の中にいると上手く会話に入れなかったり、つい的外れなことを言ってしまったり、... -

心理カウンセラーは理解者であるが味方ではない
心理カウンセラーについて誤解されている方が以外と多いのではと思う時があります。それは、心理カウンセラーとは、ご相談者様にとって理解者ではあっても、味方ではないということです。 もし、心理カウンセラーがご相談者様の味方と思われているのでした... -

許せない人を無理に許す必要はない
許せない人は忘れて自分の人生に専念する大切さ https://youtu.be/d6yyKSfbl1Y 許せない人。 誰にでもいるのではないでしょうか。 許せない人。 それは、子供時から自分を尊重しなかった親かもしれません。学校において、いじめを行った人達かもしれません... -

批判と疑いの心理:知性と感情の付き合い方
「批判」や「疑い」といった言葉は、ネガティブな印象を与えるため、あまり歓迎されないかもしれません。 しかし、これらは私たちの思考や感情と深く結びついており、決して悪いことばかりではありません。 goo辞書によると、批判には「物事を検討し評価す...