「注意」が「怒り」へ変わる時:その心理と健全な関係のために
人に対する注意が怒りの感情に変わるその理由
Index
1.「言いたくない」という葛藤:注意する側のストレス
2.「怒り」への転換:対応次第で変わる関係性
1.「言いたくない」という葛藤:注意する側のストレス
私たちは日常生活の中で、他者の行動を見て「それは違う」、「良くない」、「危険だ」と感じた時、つい注意をしてしまうことがあります。
子育て中の親御さん、職場の先輩や上司など、様々な立場での「注意」があるでしょう。
さて、この「注意」をする側の心理について考えてみたことはありますか?
実は、多くの人が「本当は注意したくない」と感じています。
それでも、相手の将来を案じたり、行動を正してほしいという思いから、やむを得ず口にするのです。
また、注意することが自身の責任や仕事であると捉え、内なる葛藤を抱えながらも注意せざるを得ない人もいるでしょう。
このように、注意をする側は、すでにその時点で内心イライラやストレスを感じています。
「言いたくないのに言わなければならない」という心理的な負荷は、想像以上に大きいものです。
さらに、「注意した後、相手に嫌われるのではないか」、「良く思われないのではないか」といった不安も抱えています。
このような心理的な重荷を背負った状態で注意をしているため、注意を受けた側が素直な態度で耳を傾けてくれれば、注意する側もある程度は気持ちが収まるでしょう。

2.「怒り」への転換:対応次第で変わる関係性
しかし、もし注意された側が、屁理屈をこねたり、聞く耳を持たなかったり、非論理的な言い訳を始めたりしたらどうなるでしょうか?
もともと心理的な負荷がかかった状態で注意をしているため、心に余裕がない注意する側は、この瞬間に冷静さを失い、脳が「怒り」に転換してしまうことがあります。
まるで、積もり積もった感情が一気に爆発するように、相手を怒鳴りつけたり、罵倒したりしてしまうかもしれません。
「相手のためを思って」という当初の目的は、相手の不誠実な態度によって、「相手を言い負かす」、「撃破する」といった全く別の目的へとすり替わってしまう可能性すらあるのです。
そして、怒りが収まった時、「一体、自分は何に怒っていたのだろう」と、戸惑いや自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。
これが子育ての場面であれば、親としての責任感から、怒っても冷静さを取り戻し、再度穏やかに注意を促す努力をするかもしれません。
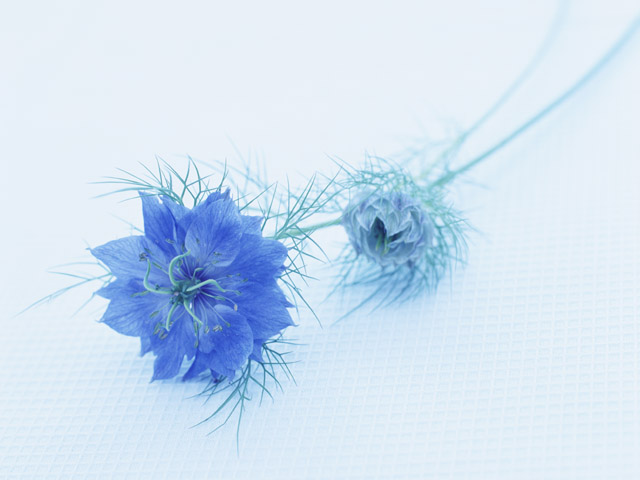
しかし、職場ではどうでしょう。「言っても分からない奴には二度と言わない」と、上司や先輩に疎まれる可能性もあります。
そうなれば、以降はまともな指導を受けられなくなり、仕事も覚えられず、業務成績は伸び悩み、人事考課でマイナス評価を受けることにもつながりかねません。
素直に注意を聞き入れていれば避けられたであろう事態であり、まさに自業自得と言えるでしょう。
相手の「心の状態」への無知や、「どうせ理解してくれないだろう」という傲慢な態度は、時として人間関係に大きな溝を作ってしまいます。
注意を受け入れる側の対応一つで、その後の関係性が大きく変わることを肝に銘じる必要があるでしょう。


















